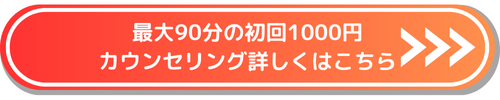こんにちは!
家族で幸せな生き方を見つけるカウンセラーの高橋和美です。
「学校に行きたくない…」「学校に行きたいのに行けない…」で
苦しんでいる子どもたち
子どもの不登校を見守りたいのにイライラしたり辛い思いをしている
お父さん、お母さんに向けてカウンセリングをしております。
「うちの子が学校に行きたがらない……」
「不登校って親の責任なの?」
「学校に行かないと将来が不安……」
このように、不登校に対して不安を抱える保護者の方は多いのではないでしょうか。
「学校に行かないのは良くないこと」「親の育て方に問題がある」「本人が弱いから」といった先入観を持つ人も少なくありません。社会全体にも「学校に行くのが当たり前」という価値観が根強くあり、不登校は「問題」として扱われがちです。
しかし、本当にそうでしょうか?
不登校をどう捉えるか?
不登校を「問題」として捉えると親も子もしんどくなります。
「問題児ではなく問題を抱えている子」なのです。
子どもが学校に行かなくなるのにはさまざまな理由があります。
それを無視して「とにかく登校させる」ことに固執すると、子どもはより追い詰められてしまいます。
学校に登校させる前に充分な心の栄養が必要なのです。
複雑に絡みあう不登校の要因
不登校の背景には、子ども自身の意思や環境要因など、さまざまな理由があります。
ただ「学校に行かないことが悪い」と決めつけるのではなく、なぜその選択に至ったのかを理解することが大切です。
子ども本人に聞いても不登校になった原因を答えられない、またはわからない場合がほとんどです。
それでも心の栄養が空っぽになっているということは言葉にはできない何かがあるのです。
✅ 学校の環境が合わない
学校のルールや集団生活がストレスになる子もいます。
いじめや先生との関係、過度な競争などが要因となり、心が疲れ果ててしまうこともあります。
✅ 学び方の違い
黒板の授業が合わない、長時間座っているのが苦痛など、学習スタイルが子どもに合わない場合もあります。
「学ぶこと自体は好きだけど、学校のやり方ではうまくいかない」という子どもも少なくありません。
✅ 心や体からのSOS
朝になるとお腹が痛くなる、頭痛がする、学校の話をすると不安そうな表情になる。
これらは心の疲れが身体に出ているサインかもしれません。
「怠けている」のではなく、無意識のうちに自分を守ろうとしているのです。
✅ 家庭環境や性格的な要因
家庭の事情や、HSC(人一倍敏感な子)の特性を持つ場合、集団生活が負担になりやすいこともあります。
不登校は「甘え」ではなく、子どもが環境に適応しようとした結果として起こることが多いのです。
このように、子どもが学校に行かなくなるのは、本人が怠けているわけではなく
「学校に行くことで心や体が限界になっている」
サインなのです。
不登校は「行かない」ことが問題なのではなく、「子どもの心のSOSに気づき、早い段階で心を満たすこと」が大事です。
「学校に行かない=悪いこと」ではありません。
不登校は、子どもが自分を守るための選択であり、大人がその声を受け止めることが大切です。
お母さんの育て方が悪かったわけでもないのでお母さん、お父さんは自分を責めたり、相手を責めたりしないでくださいね。
親としてできることは
無理に登校させるのではなく
子どもが安心して過ごせる環境(最初は自宅から)をまずは作ることです。
「学校に行くこと」よりも、まずは子どもが置かれている「今」をわかろう、理解しよう、理解したいという気持ちが大切なのです。
お試しカウンセリングでお悩みをお聞かせくださいね✨